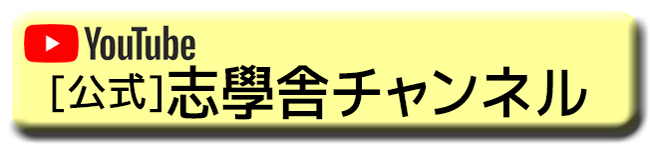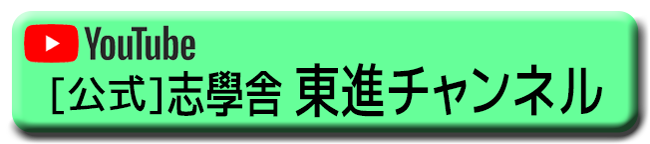コラム
水本代表、志學舎を語る⑫
思いを形に②
こんにちは。志學舎代表の水本です。

<山梨セミナーハウスからの眺望(南アルプス:2020.09.15撮影)>
1980年代後半、私が高幡本校、積先生が南平教室の責任者として教室を運営していたころ、積先生から「合宿所を作りませんか」と言われました。以前勤めていた塾では土日合宿などをしていたそうで、南平教室でも教室に通う生徒を集めて土日で泊まり込みの合宿のようなことをすでに実行していました。それを今度は塾全体でやれるように合宿所を作れないかというのです。「それはいいね」と意気投合して、まずは土地を探すことに。
いろいろなところを積先生といっしょに探しました。富士山のふもとの河口湖、奥多摩の山林など。しかしこれといっていい土地が見つかりませんでした。「やっぱり無理かな。仕方ないな。」とあきらめかけた時、「最後にもう1軒行ってみよう」と飛び込みで訪ねたのが山梨県の塩山(えんざん)駅前の不動産屋。最初に案内されたところに一緒に行きましたが合宿所には手狭な土地。「合宿所なのでもっと広い土地がありませんか」と尋ねてみると、「宅地ではないけど、こんにゃく畑ならあるよ」と言って連れて行ってくれたのが、塩山駅からどんどん上がっていった標高の高いところにあって、南斜面で見晴らしの良い土地でした。
正面に南アルプスの山々を一望できる眺めの良い場所でした。その眺望がとても気に入って「ここならば」と思いました。しかし、手元にお金があるわけでもなかったので、「もし銀行から融資が受けられなかったらこの契約は無効とする」という特約条項をつけて購入契約をしました。
それから今度は銀行探しに。高幡教室の開校時に世話になった当時の国民金融公庫に借り入れの申し込みをするとOKが出ました。これで土地が買える。
しかし合宿所を建てるにはもう一つ難題が。もともと山の斜面のこんにゃく畑だったのですから、まず斜めになっている土地を平らに整地して、それから合宿所となる大きな建物を作らないといけない。それにはさらにお金がかかる。そこで追加の融資を申し込むと、これもOKに。当時はバブル時代。土地神話で宅地ばかりでなく畑や山林の土地の値段も年々上昇していたので、購入予定の土地・建物を担保に入れることで融資が認められたわけです。しかし、借金の総額はそれまで借りたこともないほどの大きな金額となり、正直なところ「これが最後の借金」と腹をくくったのを覚えています。
資金的な手当てがつくといよいよ工事へ。積先生が建物のラフデザインを描き、それをもとに業者が設計図を作成。最初の積先生の案では風呂が無かったのですが、「やっぱり風呂はつけようよ」と私が言って風呂を作ることに。限られた予算と相談しながら、予定していた部屋の一部をカットしたりと試行錯誤して、ついに、1988(昭和63)年、合宿所が完成。「山梨セミナーハウス」と名付けました。
さて、いざ、数十名単位の生徒をセミナーハウスまで連れて行こうとすると、今度は交通手段が問題に。電車で塩山駅まで行ったとしても、そこから車で30分ほど上がったところなので、大人数の移動がネックに。それなら塾でバスを買って東京から山梨の合宿所まで直接連れて行けばいい、という話に。実際にはリース契約でしたが、塾専用のバスも用意しました。その運転のために積先生には大型車の運転免許をわざわざ取得してもらいました。
こうして積先生の言葉がきっかけとなって山梨セミナーハウスが完成しました。以後、土日や祝祭日を利用した中学生の勉強合宿や、小学生への野外体験型合宿など、寝食を共にした生徒指導や交流の場となりました。普段の教室で勉強に打ち込む表情とはまた異なり、食事や野外活動での生き生きとした生徒たちの姿に接することができて、私自身もとても楽しく、たくさんの元気をもらいました。
もし、積先生と出会っていなかったら、積先生の提案を聞いていなかったら、あきらめかけた時に最後にもう1件だけと塩山の不動産屋に行かなかったら、銀行が融資してくれなかったら、山梨セミナーハウスはできていませんでした。こうした機会に恵まれたことに本当に感謝しています。

<完成したころの山梨セミナーハウスでの集合写真。塾のバスも映っています。>

<庭ではよくバーベキューをしてみんなで食事をしました。>

<私もよくバーベキューで肉を焼きました。>

<館野君(現 南大沢教室長:写真右下)も引率者としてよく来ていました。>

<小学生は庭にテントを張って野外キャンプ体験も。>

<夏にはプールも。>

<夜は寝袋で寝ました。>

<セミナーハウスの教室内の様子>